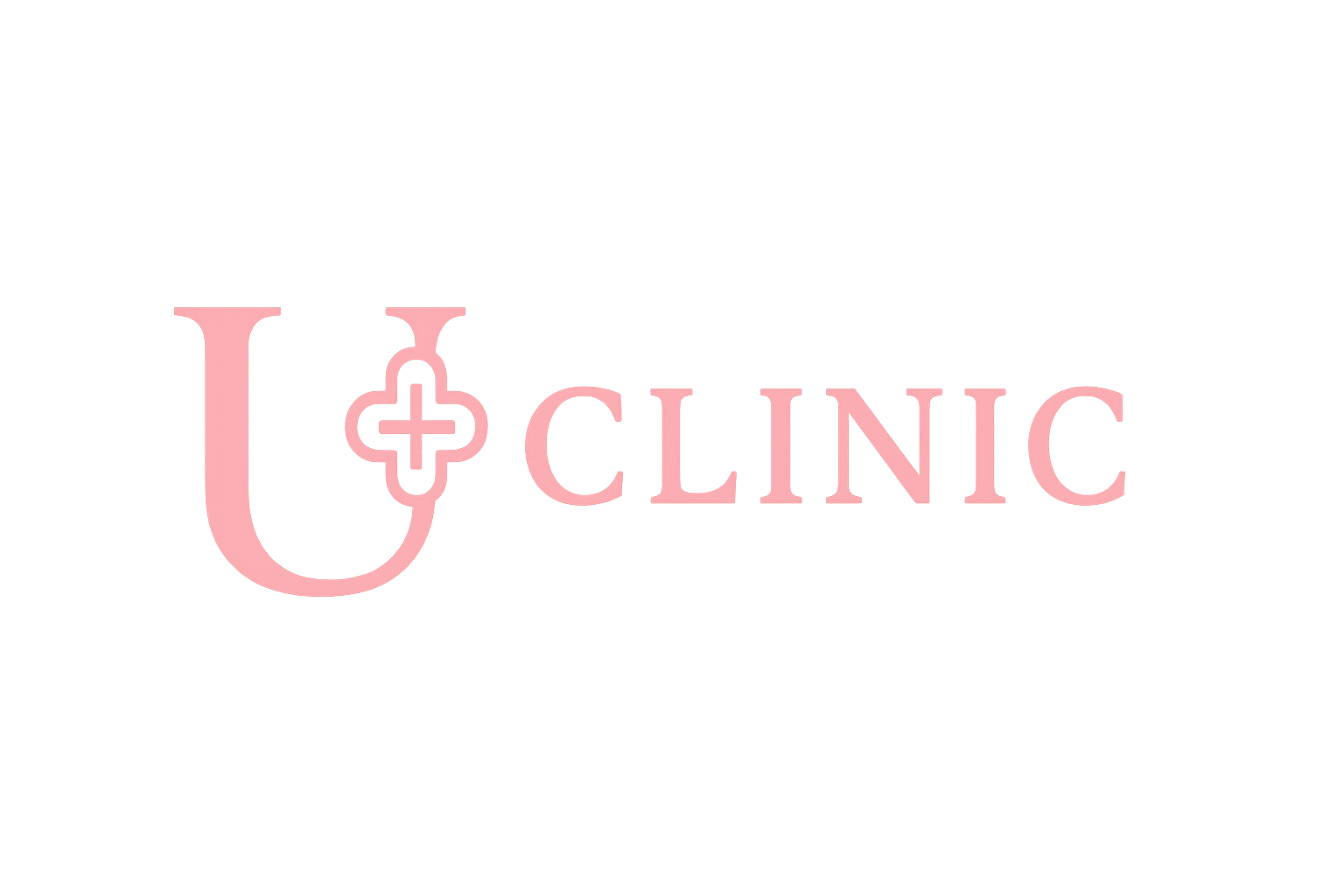「胃カメラはつらい」「大腸カメラは恥ずかしい」——そんなイメージをお持ちではありませんか?
内視鏡検査は、がんをはじめとした消化器系疾患を早期発見・治療するために欠かせない検査です。近年は、鎮静剤の併用や経鼻内視鏡の導入などで、苦痛の少ない検査が可能になっています。
この記事では、内視鏡検査の種類・目的・流れ・注意点・費用など、初めて受ける方でも安心できるよう、丁寧に解説していきます。
1. 内視鏡検査とは?
内視鏡検査とは、体内にカメラ(スコープ)を挿入し、臓器の内部を直接観察する検査のことです。口または鼻、肛門からスコープを挿入して行います。
主に行われる2つの検査:
- 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ):食道・胃・十二指腸を観察
- 下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ):大腸全体を観察し、ポリープの切除も可能
2. 胃カメラ検査 ― 胃がんや胃炎の早期発見に
■ どんな人が受けるべき?
- 胃の痛みや不快感がある方
- 胃もたれ、胸焼け、ゲップが続く方
- ピロリ菌感染の既往がある方
- バリウム検査で異常が出た方
- 50歳以上の方(胃がんリスクが高まる)
■ 経口 vs 経鼻:どちらが楽?
- 経口内視鏡:口から挿入。映像が鮮明で処置にも向くが、嘔吐反射が強い方にはつらい場合も。
- 経鼻内視鏡:鼻から挿入。管が細く、違和感が少ない。会話も可能。
※鎮静剤を併用すれば、寝ている間に終わるケースも多くなっています。
■ 検査の流れ
- 前日は21時までに食事を終える
- 当日は朝から絶食(水分は可)
- 医療機関で局所麻酔+鎮静剤を使用
- 検査時間は約5〜10分
- 検査後は休憩してから帰宅
3. 大腸カメラ検査 ― ポリープ切除でがんを防ぐ
■ どんな人が対象?
- 便に血が混じる・便通異常がある方
- 健診で便潜血陽性となった方
- 大腸ポリープ・がんの家族歴がある方
- 40歳以上で未検査の方
大腸がんは早期発見で90%以上が治る病気。大腸内視鏡検査によるポリープ切除は、がん予防に非常に有効です。
■ 前処置が最大のハードル
大腸カメラの特徴は、検査そのものより“事前準備(腸管洗浄)”の大変さにあります。
- 前日は消化の良い食事を取る
- 当日は朝から下剤を2リットル服用
- 腸が空っぽになるまで排便を繰り返す
病院によっては、前日夜からスタートするパターンや、洗浄液の量を減らす対策も導入しています。
■ 検査の流れ
- 事前に食事制限と下剤で腸をきれいに
- 病院でモニターを装着し、鎮静剤投与
- 肛門からスコープを挿入(15〜30分程度)
- 異常があればその場で組織採取やポリープ切除
4. よくある不安・疑問Q&A
Q1:痛みはありますか?
→ 鎮静剤を使えば、ほとんどの方が「気づいたら終わっていた」と言います。痛みや不快感を最小限にするために、医師の技術も重要です。
Q2:恥ずかしくないですか?
→ 検査時は専用の検査着を使用し、プライバシーに配慮されています。女性検査技師・女性医師を選べる施設もあります。
Q3:費用はどれくらい?
→ 健康保険適用で、自己負担3割の場合:
- 胃カメラ:約3,000~6,000円前後
- 大腸カメラ:約6,000~10,000円前後(ポリープ切除がある場合は追加費用あり)
※健康診断や人間ドックでの自費検査は1万〜2万円以上が目安です。
5. 内視鏡検査で発見される主な病気
胃カメラでわかる病気
- 逆流性食道炎
- 食道がん
- 胃炎・胃潰瘍
- 胃がん
- ピロリ菌感染
大腸カメラでわかる病気
- 大腸ポリープ
- 大腸がん
- 潰瘍性大腸炎
- 虚血性腸炎
- 過敏性腸症候群
6. どこで受けられる?受診のすすめ
内視鏡検査は、以下のような施設で受けられます:
- 内科・消化器内科クリニック
- 胃腸科専門病院
- 総合病院・人間ドック施設
最近では、女性専用の内視鏡外来や、土日も対応しているクリニックも増加中。事前予約が必要なことが多いため、早めの計画が大切です。
7. まとめ ― 検査は「怖いもの」から「安心のため」に
内視鏡検査は、単なる苦痛なイベントではなく、あなたの将来を守るための重要な予防医療です。
- 胃や大腸に違和感がある人はもちろん、
- 健診で便潜血が出た方、
- 家族にがん歴がある方、
- 40歳を過ぎた方は、
ぜひ一度、検査を前向きに検討してみてください。
“検査を受ける勇気が、命を救う”
そう考えて、あなた自身の健康に一歩踏み出してみませんか?